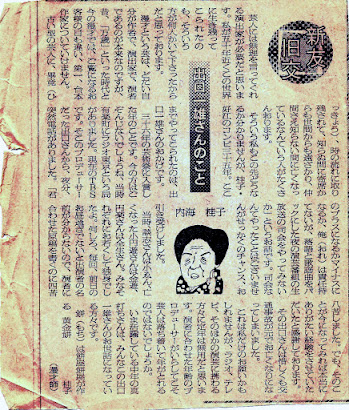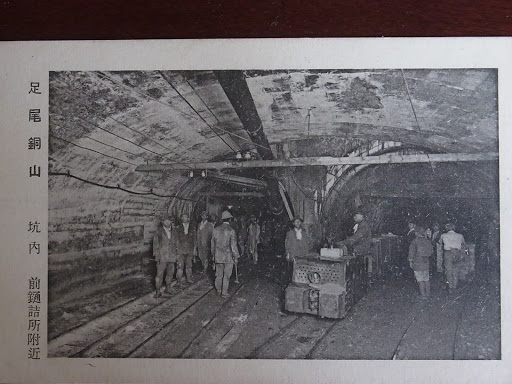物置で『戦争論妄想論』という本を見つけて読んでいる。小林よしのり『新ゴーマニズム宣言special戦争論』のカウンター本として、1999年夏に出た。装丁も『戦争論』を想起させるデザインになっている。
『戦争論』が出たのは1998年夏。文字通り大ヒットになった。新聞の下半分にでかでかと広告が打たれ、売れに売れた。
実は私も買った。思想的には相容れないが、読まずに批判するのもまずいと思って買って読んだ。読んでいるうちに吐き気を催した。右翼トンデモ本の焼き直しのような主張が延々と繰り返され、しかもマンガだからそれが強烈にインプットされる。これがベストセラーとなることに、改めておぞましさを感じた。そして、その売り上げに自分も貢献してしまったことを心底後悔した。だから、以後私はこの手の本を買わないことにした。
さて『戦争論妄想論』についてである。
この本のあとがきでは「本書は『戦争論』と対決するという試みの構想としてスタートした」と書かれている。『戦争論』が大きな支持を集めることへの危機感がこの本を生んだと言っていい。宮台真司、姜尚中、水木しげる、石坂啓、中西新太郎、若桑みどり、沢田竜夫、梅野正信という豪華執筆陣が、「「国家と個人」「戦争と平和」の論争に答え、『戦争論』を根底から撃つ!」と帯にはある。
しかし、この試みは成功したとは言い難い。
『戦争論』で勢いづいた歴史修正主義はネット右翼を生み、果てはヘイトスピーカーをも生み出した。(事実、「『戦争論』で目覚めた」というヘイトスピーカーも少なくない。)
また、この流れは憲法改正を目論む大日本帝国復権主義者にも力を与えた。今や現政権の中枢や、その取り巻きは、大日本帝国復権主義者で席巻されている。しかも、巧妙に人事を利用し、マスコミ、司法、行政も服従させる。もはや「関東大震災直後における朝鮮人虐殺」も「南京事件」も「慰安婦問題」も「諸説あり」とされ、正面切って取り上げれば攻撃を食うので、何となく口にするのも憚る雰囲気になってしまった。(何しろ原爆の悲惨さを伝える展示でさえ「政治的だ」として退けられるのである。)
こうした奔流に、『戦争論』批判は、あえなく飲み込まれてしまった。「飲み込まれてしまった」という表現がそぐわなければ、『戦争論』に目覚めた者たちの大多数には届かなかった、と言い換えてもいい。
『戦争論妄想論』、改めて読むといわゆる総花的である。それぞれ得意分野での論評で、ひとつひとつはしっかり読ませる内容になっているが、全体的に気迫に欠け、攻めあぐねている感じが拭えない。「それぞれの立場は異なるが、方向性は鮮明に出せた」というが、それは対立軸に旗を立てたにすぎなかったのではないか。むしろ私は当初の構想にあった「『戦争論』で描かれている中身に沿って、一つひとつに反論する方法」に似た、『戦争論』で描かれた虚偽やごまかしを徹底的に暴き反証するといったやり方の方が有効だったと思う。
振り返ってみれば、美しい物語、力強い語り口、誇りの回復といったものに身を委ねる快感が用意され、それに国家権力が味方する(特にここ7、8年はそれが顕著だった)。どう考えても負け戦にならざるを得ない状況だったな。
小林よしのりは『戦争論』に先立つ1996年『新ゴーマニズム宣言special脱正義論』の中でこう言っている。
「はっきり言ってわしのやったことは世論捜査のための言論暴力ですよ。(中略)正義もクソもないの。世間に正義と思わせるようやっただけ。そういう意味じゃファシズムかもしれんよ。どうぞわしをファシストとののしってくださいという気持ちだよ」
こういうやり方をしている相手である。同じ土俵に立って戦おうとしても、噛み合うはずがない。論点をずらし、隠し持った凶器で襲い掛かかってくるだろう。(今やあっち側はそんな手合いばかりである。)
現在小林はネット右翼については批判しているが、マッチョな体質に変わりはない。
また『戦争論』的なアジテーションが金になることが分かったからか、ビジネス右翼がわらわらと沸き上がった。これらがこぞって隣国攻撃や現政権擁護に走る。本屋に行けばこの手の出版物が山と積まれていて、ある意味壮観だが、その末世感たるや半端ない。
では現状を嘆くだけでいいのか。そうではあるまい。
『トリック 「朝鮮人虐殺」をなかったことにしたい人たち』(加藤直樹)、『歴史戦と思想戦 歴史問題の読み解き方』(山崎雅弘)、『「南京事件」を調査せよ』(清水潔)などは、確かな論証で歴史修正主義を正している。ツイッターでもそういったものが数多く発信されるようになった。
歴史を捻じ曲げ、隣国憎悪を煽り、大日本帝国的価値観を復権しようとするものは、やっぱり粘り強く潰していくべきなんだよな。
その意味では、あの当時『戦争論妄想論』が出たのには、やはり大きな意義があったのだと思う。