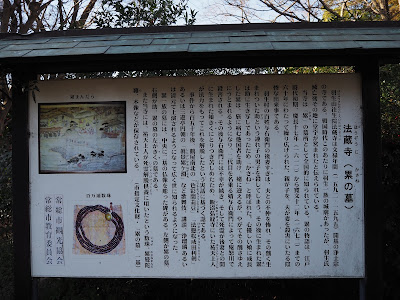七代目橘家圓太郎という音曲を得意とする噺家がいた。明治35年(1902年)生まれ、昭和52年(1977年)76歳で没。昭和52年というと私は高校生になっていて落語ファンではあったが、圓太郎は知らなかったなあ。
大正14年(1925年)、初代橘ノ圓(浮世節の大看板、立花家橘之助の夫である)に入門するも、昭和10年(1935年)師匠夫婦が京都の水害で死去。巡業に来ていた蝶花楼馬楽時代の八代目正蔵の内輪になった。
『古今東西落語家事典』には、「前職が代用教員という変わり種」「学芸肌のところもあり、創作が縁で作家正岡容との交流もあり、その尽力もあって、昭和十八年四月、七代目橘家圓太郎を襲名した。ひところ桂文楽の門に列したが、しつけの厳しさに耐えかね、居心地すこぶる悪しとノイローゼ気味、再び林家正蔵門に戻って自在な地位を確保した」という記述がある。この辺りのいきさつが、八代目正蔵戦中日記』に出てくるのだ。
まず、昭和18年1月23日の記事。
夜、正岡氏の宅を訪ね円太郎の件を談合したが、彼は私の家へ来ないから弟子にはしないなんて事を云はずに、弟子は持たぬ主義だからと弁明したのは宜かったと思った。
昼間からいやきのうから気のふさいでゐたような気分がこれで一掃された。
この時点で早くも「円太郎」と呼んでいる。前年の記事では「百円」で登場していて、内輪として働いたり独演会に出演したりしているが、圓太郎襲名に関する記述はない。その年(昭和17年)、正蔵は9月半ばから12月まで南支慰問に参加しており、その間に正岡の尽力があったのかもしれない。
この記事は圓太郎襲名が決まった頃か。この記述から詳細は分からないが、推察するに、圓太郎襲名に際し、内輪という曖昧な処遇にしておくのではなく、正式に弟子にしてはどうか、と持ち掛けられた正蔵が、「私は弟子は持たぬ主義だから」と辞退したのではないかと私は解釈した。ただ、正岡容が圓太郎を自分の弟子にすることを辞退して、正蔵に預けたようにも読める。編者は「円太郎を弟子にする件」としてあるから、正岡が辞退したということにしている。この直前の何日かをカットしているので、その辺りに何かそれを裏付けることが書いてあったのかもしれない。
結局、「雑務の方面では百円の円太郎を文楽師内輪にしてやる話。(S18・3・4)」とあるように、圓太郎を八代目桂文楽門下にする案が浮上する。
そして3月8日、正蔵は正岡容と文楽の家に赴く。
正岡君と御徒町駅で落合ひ、文楽師宅を訪ひ正式に百円改め円太郎を弟子にして貰ふ話をすゝめ承諾してもらった。
3月17日には圓太郎を連れて黒門町へ。
御徒町の駅で百円。正岡。私と三人で落合って文楽師の家へ行く。正式に百円を入門させる事に話を進めてあるので今日はその当日だ。文楽会なので連れ立って本郷の志久本へ皆で歩いて行った。のんびりと。
文楽会で寄席へ出抜けになるまで遊んで了った。対談会へワリ出したりなどして!
「百円」と呼んでいるから、この時点ではまだ襲名前なのだろう。この日は「文楽会」の日で、正蔵は飛び入りで対談会に出演した。
順調に進むかと見えた百円の圓太郎襲名、文楽への入門に暗雲が立ち込める。どうやら協会に話を通す前に新聞にスクープされたらしい。3月15日の記事だ。
百円あらため円太郎のニュースが東京新聞へ出た。文楽さんが非常に気にしてゐるから根岸と貞山先生へ釈明して歩いた。
「根岸」は八代目桂文治、貞山は当時の落語協会の会長である。正蔵は文楽の意向もあり、この二人の所へ釈明に行く。ところが、これが正岡容の怒りを買ってしまう。
3月29日の記事。
二十八日、雨の中を新円太郎を連れて上鈴から予定順のとほり廻って歩く。
(中略)
正岡君から電話なので四谷の家を切り上げて娘を連れて訪れた。当人は病床に在って会はなかったが要件はメモになってゐて、文治さんの所へ強制的に容さんを連行しようとした事は怪しからんといふ意味ともう一ツは私独りが附いて廻った事は僭越と思ってゐるらしい。
「上鈴」とは上野鈴本のこと。正蔵はこの日、圓太郎とともに席亭への挨拶回りをしたものと思われる。
翌日、正岡に電話で呼び出され家に行くが、当人は病気で会えないという。その代わりにメモで、3月15日の行動についてなじられた。帰宅後、正蔵は正岡に当てて釈明の手紙を書いたが、この記事の末尾には「私を呼びつけての態度は病人とは謂へ愉快なものではなかったことは事実だ」と書いている。
3日後の4月1日、正蔵は圓太郎の挨拶回りのために正岡宅へ行き、当人に会うことができた。この日正蔵は「先方の云ふ事にも一理ある。殊に私に対する愛着は非常なものでこの点感謝する」と日記に書いた。
ところが2日後の4月3日はこんな調子だ。
正岡君の所へ行ってみたら、歌子さんは針しごとをしてゐるし、当人は三十八度二分の熱があるとかで会ってはくれなかった。
万事は明日うち合せをするとの事で帰ってきた。私は少なくも愉快ではない。
これが文楽さんならこんなにカルクは扱はないだろうと思ふと心外だ。
それまで、正蔵と正岡との仲は親密だった。『八代目正蔵戦中日記』の前半部分、二人はしょっちゅうお互いに行き来し、大いに飲み大いに語り合っている。しかし、圓太郎襲名の辺りで、どうもおかしな方向に向かっていく。
4月4日にはこんなふうに心情を吐露している。
正岡君、近頃の態度は、あまり親しすぎて却ってお互ひが敬愛出来ないのか。
私の方が崇敬しないのが悪いのか。
ほんとに暫く遠ざかった方がいゝのだと思ふ。
それでも圓太郎襲名披露の会の準備は進む。
二十二日、八王子に円太郎の会がある。
その打合せを文楽さんと相談して皆に通達した。(S18・4・20)
そして八王子の会は盛況に終った。
八王子の円太郎の会、晴天にて盛会裡に終る。扇遊さんと右女助君に口上を手伝って貰ったが旨く喋れなかった。こんな事にも修業が入る。
五打目の師匠左楽師のうまさが思ひ出された。(S18・4・22)
正蔵は口上を述べた。さぞ、ほっとしたことだろう(ちなみに五代目左楽は口上の名人として知られている)。しかし、そのまま順調にはいかない。
文楽さんの所でのはなし。
一日から出番があるのに円太郎が出演しないので不思議に思ってゐると、正岡さんの打った電報の返電にアタマガオカシイ。としてあったそうだ。原因はなんだか。どんな様子だか目下のところ私の所では皆無わからない。(S18・5・4)
今度は圓太郎本人がノイローゼになってしまったようだ。その原因は、この襲名にかかるごたごたにあったらしい。5月17日の日記に、正蔵は以下のように書いている。
文楽さんのお骨折で、新宿の高座済んだのち連れだって、正岡氏を訪ね、文治さんの宅同道云々の事に就いて謝罪してくる。
円太郎もこの事については一ト方ならず心痛して病気になって了った由だから、私が謝って正岡氏も快よくなり、円太郎も安心し。文楽会も無事に続けられゝばこんな結構なことはないのだ。(中略)但し私はどんなに偉くなっても決して他人は謝罪なんかさせないつもりだ。
この日、正蔵は文楽の仲立ちで正岡に謝罪し、一応和解した。とはいえ、彼の心の中のわだかまりは消えていない。それが、前回の記事にある文楽会での正岡の暴言で爆発することになるのである。
結局、正蔵と正岡の和解は昭和20年を待たねばならなかった。1月26日の日記から。
林伯猿氏の骨折りで、正岡氏と仲直りの会を若よしさんで催す。お立合に四代目と文楽さん。どっちも先輩だから私が東道の役(主)をつとめる。(中略)たいして言葉も交へずに、もうお互ひの気持ちはうちとけて一緒の路を帰り乍ら、旧友の二人になれてゐたうれしさは感謝していゝ事だった。林伯猿氏に御礼を申し上げる。
一方圓太郎はその後、「(文楽の)しつけの厳しさに耐えかね、居心地すこぶる悪しとノイローゼ気味、再び林家正蔵門に戻って自在な地位を確保した」という。
七代目橘家圓太郎について『古今東西落語家事典』はこう結んでいる。
賢人林家正蔵の懐ろの大きさにはつねに敬服しており、「正蔵トンガリ座」の主軸として柳家小半治、土橋亭里う馬という錚々たる野武士集団の一翼を担って、つねに楽しい噺家であった。人柄は至って温厚、「八王子の師匠」と若手にも人気があり、懇切丁寧なることこの上なかった。
デグチプロの出口一雄は、圓太郎に10万円の仕事を世話した時、本来はマネジメント料1割の1万円を取るところを、「圓太郎から1万取れるか」と言って、10万そのまま圓太郎にやったという。しかも、ギャラの支払いは銀行振り込みだったため、ポケットマネーから現金で手渡した。そういうことをさせる魅力が圓太郎にもあったのだと思う。
それにしても、稲荷町の人間の大きさはどうだ。落語協会分裂騒動の際、師匠圓生に捨てられた三遊亭好生に手を差し伸べたのも、八代目林家正蔵であった。